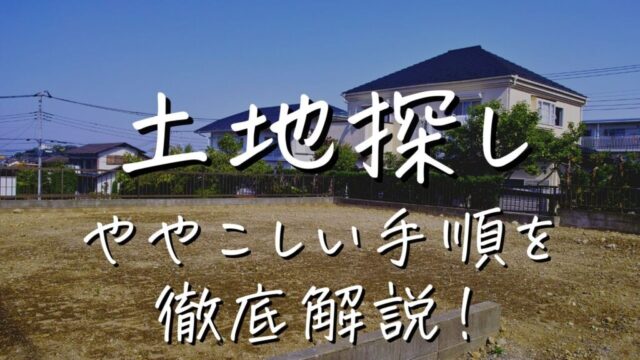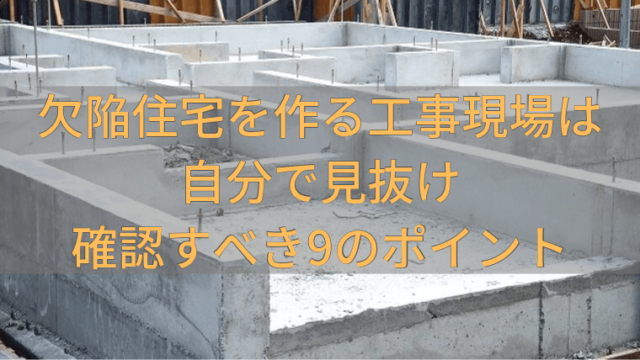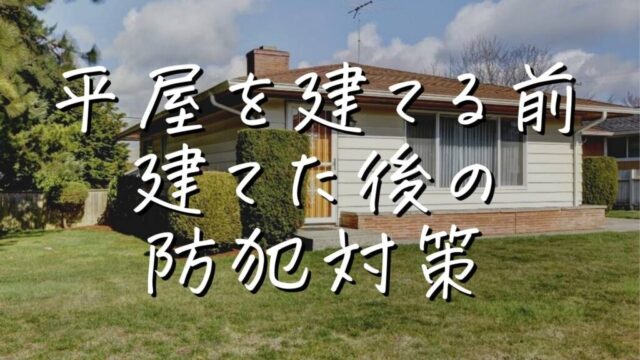住宅には、様々な工法があります。
例えば木造、RC造・鉄骨造・軽量鉄骨・ユニット工法などがあがります。
更に、木造の住宅でも在来軸組み工法やツーバイ工法などいくつかに分けることができます。
この記事を見てくれている方は、何かしら「木造住宅に興味がある方」、もしくは「今木造住宅を建築中で雨が心配だ」という方ではないでしょか?
木造住宅を建てる施主は工事中に不安になる要素の1つが雨に関してです。
木造住宅はもちろん木材が材料となっているので、なんとなく木が雨に濡れるのは良くないと素人でも分かることです。
なので工事中の、特に上棟工事(骨組みが立つ時)前後の構造体がむき出しの状態で天気が不安定だと非常に不安になります。
今回は木造住宅を400棟以上担当した私が現場監督をしていて、また同じ現場監督の仲間の話などから「実体験を中心に木造住宅と雨に関しての話」をしたいと思います。
今回の内容は主に木造住宅の上棟前後の話になります。


下の一覧でまとめられている記事は実際に元現場監督の私が新居を建てたときに工事中の状況を毎週解説した記事が載せてあります。
ぜひ一緒に読んでみてください。

木工職人のハンドメイドショップ【Twigs&Dwarf】

記事を読む前に1つ宣伝させてください!
これまでの木工職人の経験と知識を活かした、ハンドメイドショップを立ち上げました。(元現場監督で現在は木工職人としてものづくりに携わっています。)
「あなたの暮らしに木のぬくもりを」をテーマに新しい生活にそっと取り入れたくなるような木製品を数多く取り揃えています。
木材の素材感を活かした商品作りを心掛けているので、もし少しでも興味がある方は一度ハンドメイドショップをチェックしてみてください。
木造住宅は絶対に雨に濡れてはいけません。
結論から言うと木造住宅が雨に濡れて良いわけがありません!!
そりゃそうです。
住宅メーカーの担当は「多少濡れても大丈夫」と必ず言う

ですが、住宅を建てると住宅メーカーなどの営業や現場監督は口を揃えて「多少の雨なら大丈夫です」といいます。
確かに1日ぐらいの雨ならほとんど問題はありません。
しかし、これは1日雨に当たっても、その後適切に風通しが良く日に当たる環境である場合です。
では、工事現場ではどの現場でも適切に乾燥させているのか?
また含水率を計測しているのかというと、全くできていません。
含水量:木材にどれだけ水が含んでいるかを表す数値
ではなぜ担当者は口を揃えて雨に濡れても大丈夫というのか?
それははっきり言って、お客様を安心させるためです。
年間何百何千棟と建築する住宅メーカーは絶対に雨に当たる工事現場も出てきます。
ですが、その都度雨で工事の予定を伸ばしてばかりでは儲けがでません。
ましてや、雨が降るたびにお客様から欠陥扱いされても困ります。
なので、最初の段階ではっきりと大丈夫とお客様を安心をさせるのです。
ここだけの話ですが、
「雨に多少当たっても大丈夫」どの現場監督も営業もただの決まり文句でした。
でも本当は「雨が連日降っててやばいな……」なんてこともありました。
なので、「雨が降っても大丈夫」という言葉で安心しないようにしましょう。
下記の記事は自分でも現場を見る目を身に付けるためのポイントを紹介しています。
┗欠陥住宅を作る工事現場は自分で見抜け 確認すべき9のポイントを紹介
梅雨や豪雨などで木材が濡れるとカビが発生する
日本の梅雨の時期や台風の時期は何日間も雨が続き、強烈な雨風が木材を濡らします。
こうなってしまうともう完全にダメです。
最悪の場合、床下がカビだらけになったり、フローリングやその下の合板までカビが生えたりと「カビだらけのお家」が完成します。
また、壁に関してはグラスウールなどの断熱材は雨に弱いので柱や壁下地に含まれる水分で同じくカビが発生する恐れがあります。
では、もう少し詳しく工程と場所ごと話していこうと思います。
床下の空間が水が溜まる危険性

上棟工事前で、土台や床下地合板の施工が終わった状態で雨が降ると危険なのが、ブルーシートなどで雨養生をしても、どこかしら床下まで雨が溜まっていってしまいます。
この時、床下断熱という断熱材も濡れます。
この床下断熱は今ではいろんな工法がありますが、グラスウールやポリスチレンフォームが主流となっています。
特にグラスウールは濡れると断熱性が落ちるだけでなく、一度吸った水がグラスウールから抜けずに腐食やカビなどの原因になる場合があります。
また、床下に溜まった水もそのままにしていると、床下が常に水があるので土台や床下地合板が同じく腐食やカビの発生原因となるわけです。
床下は基礎と土台の間に通気を設ける場合がほとんどですが、水たまりが大きすぎるとお家が完成しても乾いていないなんてこともあります。
とにかく床下に水が残っているのは腐食やカビができる可能性が非常に高い場所なので注意が必要となります。
床下地合板が濡れることによる危険性

床下地合板とはフローリングを張る前に張ってある24~28mmの厚い床下地のことです。
工法は各社違うので様々ですが、今ではほとんどがこの床下地合板を入れています。
そして、この床下地合板はいつ工事するかというと、上棟工事前がほとんどです。
少し前までは上棟工事後に床下地を張ることが多かったのですが、上棟工事中に床下地が完成している方が安全であり、工程的にも良いということで上棟に先行して床下地を張ることが増えました。
ということは、上棟工事までの間、木製の床下地が外に敷かれたままになるというわけです。
この状態で雨が降ったらどうなるかというと、床下地はびちゃびちゃ、更には床下地を伝って床下に水たまりとして溜まります。
では、住宅メーカーの方に「床下地が濡れるのが心配だ」というと、どのような答えが返ってくるか。
ほとんどが、
「大丈夫です」
「乾くから心配いりません」
「ブルーシートで養生しているので大丈夫です」などお客様を安心させる回答をしてきます。
ですが、この言葉はお客様を安心させる決められた言葉であり、絶対に安心してはいけません。
僕からみなさんに伝えたいのは、
「雨が降った時ほど現場に足を運んでいただきたい」ということ。
床下に溜まった水たまりはそんなにすぐに乾きません。
そして、完成までには乾くかもしれませんが、何週間と水が溜まったままだと、床下は常に湿った状態なので木材には良くない環境が続いているということです。
床下地合板が濡れると、カビなどの発生はもちろん膨らんだり、反ったりと材料の品質としても良くありません。
雨によって膨らんだ材料は乾くことが合っても一度膨らんだ材料は元の厚さに戻りません。
では、膨らんだり、反った材料はその後どのような影響が出るかをご説明します。
床下地合板が雨で膨らんだら
床下地合板が濡れて膨らんだらまずフローリングの不陸に影響がでます。
不陸(ふりく):凹凸があること、または水平でなく傾きがあること。
濡れた場所と濡れてない場所で材料の膨らみ加減が変わるので凸凹した状態の下地でフローリングを張ると凸凹したままの床が完成してしまいます。
そして、一番怖いのが床を止めている釘が抜けやすくなることです。
一回打ち込んだ釘が材料が濡れて変形したりすると、元の状態に比べて抜けやすくなります。
そうなってしまうと、強度だけでなく音鳴りなどにも繋がってしまいます。
せっかくの新居なので歩くたびにきしむ音が鳴るのは嫌ですよね。
床下地合板が反ると
床下地が反っても、膨れと同じくフローリングの不陸に影響が出るのと、釘のゆるみによる音鳴りに繋がります。
特に床下地が反ってしまうと欠陥住宅の代表例でもあるビー玉コロコロ状態になってしまいます。
柱、梁などが濡れると壁断熱に影響が出る可能性がある

柱、梁は基本多少の雨であれば、ちゃんと乾かせばほぼ問題はありません。
しかし、怖いのが何日も雨に当たった状態で乾ききる前に壁断熱を入れること。
柱、梁が濡れたまま壁断熱を入れるのは危険!!

木造住宅の壁断熱の主流はグラスウールです。
このグラスウールは雨など水分や湿気に弱い性質があります。
よく壁の雨漏りなど欠陥住宅として取り上げられる木材と一緒に腐食している綿みたいなものが壁断熱のグラスウールです。
このグラスウールは建物の柱などに固定をして施工をします。
なので、もし柱が湿ったままだとグラスウールに柱の水分が移り腐ってしまう可能性があります。
また、腐らなくても壁断熱の性能が落ちる可能性もあります。
グラスウールは一度濡れて性能が落ちて、乾いても性能が戻ることはありません。
しっかりと壁断熱と触れる木材は乾燥させなければいけません。
化粧柱、化粧梁が濡れるのは雨染みが残る

化粧柱、化粧梁はその名の通り、化粧材として見せる柱、梁のことです。
なので、上棟した時の状態がそのまま見えるわけです。
化粧柱、梁は無塗装の時もあれば、塗装をすることもありますが、場所によっては雨による水垂れの原因で水跡になってしまうことがあります。
この水垂れの跡が付くとなかなか落ちません。
この化粧柱、梁を完全に雨に濡れないようにすることはほぼ無理だと思ってください。
濡れないようにしっかり養生をしても、100%防ぐことはできません。
では、マイホームの化粧柱、梁を守るにはどうすればいいか、
まず一番はやはり雨に当たらないことです。
それ以外の方法は、後付けで化粧柱、梁を付けるということです。
上棟時には施工せず、雨に当たらないようになってから後から施工をする方法です。
通常、化粧柱、梁は構造としても兼ねていますが、後付けの場合は構造計算に含まず完全にデザインとして取り付ける化粧材として取り入れるということです。
これは、あなたが一人で決めることでもないので、住宅会社と相談して決めるのがいいでしょう。
大安と晴天どちらがいい日?晴れを優先すべき

だいたい上棟の日程は大安など日がいい時を好む方が多いでしょう。
もちろん一生に一度のマイホームを仏滅など日が悪い日はちょっと引けますよね。
僕からお伝えしたいのは、
「大安」に合わせてを天気が悪いのに無理して上棟をする必要がありますか?
ということ。
『現場監督をしていて思ったのが、一番良い日というのは上棟の前後一週間雨の予報がない日です。』
確かに仏滅で上棟はちょっと思うかもしれませんが、これまでの話を読んで木造住宅にとって雨は良くないことは分かっていただいたと思います。
まずは、建物に一番いい日を選ぶというのも一つの選択だと私は思います。
元現場監督の私がマイホームを建てたときはこうした
では私が、マイホームを建てたときはどうしたかお伝えします。
まず説明しておくと、私がマイホームを建てたのは現場監督を辞めて、以前の会社とは全く関係ない住宅メーカーにお願いしました。
これは、現場監督を辞めたきっかけと同時に移住をしたからになります、
まず、担当の営業と設計、現場監督に伝えたのが、
「1階の床下地合板施工~上棟までで雨の可能性があるなら工事は中止して上棟は延期してください」
とはっきり伝えました。
その代わり、「上棟日は仏滅でも関係なく上棟日にしてもいい」
それと「引き渡しに間に合わなかったら伸びてもいい」とお伝えしました。
つまりは、第一に住宅の品質を優先してくださいということです。
この雨に当てないということだけはマイホームの工事で強く言いました。
それ以外はある程度緩くお付き合いさせていただきました。
それほど木造住宅には雨を当てたくなかったということです。
幸い運が良く、着工から外壁工事前の間一日も雨が降らず、一切木材に雨が当たることなくマイホームは完成することができました。
下記は実際に私の新居の工事状況を解説している記事になりますのでよろしければ合わせて読んでみてください。
┗新居の工事状況 年末年始に向けて 土台、床施工完了
┗新居の工事 上棟工事編元監督が解説します
木造住宅が雨に濡れても大丈夫か:まとめ

今回は木造住宅が雨に当たってもいいのか、ということで書いてみました。
まとめると、柱梁などなら多少雨に濡れてもほとんど問題はありません。
ただ、化粧材として使用するところは雨染みに注意しましょう。
また、雨に当たってもちゃんと乾いてから出ないと壁断熱の性能に影響が出る、またはカビの発生につながる可能性があるので注意が必要です。
そして木造住宅で一番気を付けなければいけないのが、上棟前に施工をする1階の床下地合板です。この下地合板は一度濡れるだけで膨らんだり、反りが発生してフローリングの不陸などの原因になります。
また、床材なので雨が溜まりやすく水を含みやすいので水が抜けにくく、腐食やカビの可能性があるので一番注意しましょう。
もし、この記事を読んでいる人がマイホームをこれから建てるのであれば、まずは雨に当たらないようにすることを現場監督に入念に話してください。
多少言ったぐらいでは少しくらいの雨なら大丈夫ですといわれて終わります。
品質に関しては、こちらの記事も注目です。
最後にはっきりいいます。
木造住宅は油断すると簡単にカビが発生します。
マイホームの品質を守るためにも今回の内容を参考に新居の工事を迎えていただきたいと思います。